「人」より「政党」、「地域や団体」より「国」、確かにそれは小選挙区制が導く論理的帰結なのでしょう。
しかし、「掲げられている政策を実現可能性も含めてもっとじっくり吟味する」は小選挙区制がもたらす論理的帰結ではないということが見落とされていたように思われます。
自民党内における政策決定過程は相変わらずの総務会システムであり、執行部が公募で選ぶ候補者も(様々な分野で地道に経験を積んだ政策通ではなく)若くて華々しい経歴を持った人物になりがちだというのも政策精査に対するインセンティブ欠如が原因であるように思われます。
つまり、有権者は意外なほどに個々の政策を見ておらず、それよりも、政党や候補者がどのような原則や信念のもとで動いているか、あるいは、どのような原則や信念のもとで動きそうかということが重視されているような気がします。
そういった投票態度は「候補者個人ラベル」とでも表現できるのではないでしょうか。
有権者がどれくらい政策について細かく見るべきなのか、あるいは、現実問題として個々の有権者が政党や候補者が掲げている/実行した政策ひとつひとつをつぶさに精査して検討できるのかというのは分かりませんが、もし、政治制度改革が「政策」という面に対して影響を与えたかったのであれば、もっと直接的に有権者のインセンティブに働きかける何かが必要だったのだと思います。
個人的には、やはり政権交代への圧力がなければ政党単位における大胆な政策の転換や、有権者へのつぶさな製作説明などは行われづらいと思いますので、ある程度思い切って、常に野党が有利になるくらいの政治制度をつくったらいいんじゃないかと妄想したりします。
ただ、学術的には、参議院や地方議会に残る中選挙区制度が野党の結集や強力化を妨げているという議論もあるようなので、もしかすると、逆に「小選挙区制の徹底」が足りないのかもしれませんね。
(そういった学術的議論は「分裂と統合の日本政治」等で語られています)
結論
学術書だけあって読み応えのあるいい本です。
研究者ならではの視点からデータを収集・分析しているのが好印象ですね。
多少、論点が散漫すぎて全体では何を論証してみたいのか(全体としての主張)が分かりづらいところですが、まさに、政治制度改革に対しての客観的な検証集(実験結果の羅列)として見ると面白いのではないでしょうか。
政治のダイナミズムを(俗っぽい比喩や過度にイデオロギー的な観点というよりは)学術的な観点から見てみたいという人にお薦めです。
当ブログを訪問頂きありがとうございます
応援クリックお願いします!











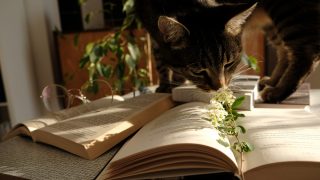




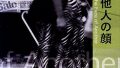

コメント