本ブログで紹介した社会学系の書籍からベスト5を選んで掲載しています。
私の好みもあり、「社会経済学」的な本が中心となっております。
第5位 「コラプション なぜ汚職は起こるのか」レイ・フィスマン
経済学者であるフィスマン教授と政治学者であるゴールデン教授が「汚職」について共同で著した本になっております。
「汚職」の発生を一種の均衡として捉え、元々「汚職」の少ない地域では「汚職」が起こりずらく、「汚職」の多い地域ではますます「汚職」蔓延るインセンティブが存在するという前提を下地に、低汚職国と高汚職国の特徴や、「汚職」の高低を左右する条件などが明らかにされていきます。
経済的に豊かではない国でも低汚職国と高汚職国に別れるのだという指摘や、政治制度はあまり汚職の蔓延と相関関係がないという分析、高汚職から低汚職に移行するためにはどのような社会的条件が必要なのかといった点が興味深く、珍しい題材だけに「汚職」に関しては鉄板の一冊なのではないかと思います。
「汚職」というテーマに興味がある方は是非、手に取って頂きたい書籍です。





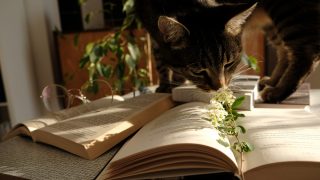





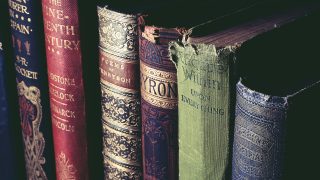





コメント