「2001年宇宙の旅」や「幼年期の終わり」で知られるSFの巨匠、アーサー・C・クラークの作品。
1956年に出版された作品ですが、2009年に新訳版が出るなどいまでも根強い人気を誇っております。
そんな本作、SFの人気作品というだけあってSF的な設定や世界観は魅力的で面白いと感じましたが、肝心のストーリーがやや冗長で起伏に欠けていると思いました。
序盤では閉じられた世界から新しい世界に主人公が踏み込むまでが長すぎ、終盤では主人公が宇宙に旅立ってその現況を眺めるという展開にしてしまったことで風呂敷が広がり過ぎて展開が拙速かつ大味になっています。
あらすじ
物語の舞台は遥か未来の地球。
ダイアスパーという都市では人間生活の全てをコンピュータが管理しており、生誕や死さえもその例外ではない。
人間のデータは全て「メモリーバンク」に記録されており、人間は両親の身体からではなく「メモリーバンク」から生まれ、そして死にたくなったときには再び「メモリーバンク」へと還り、時間をおいて新しい肉体を得て生まれ変わるというサイクルを繰り返していた。
人間の一生は主にコンピュータが提供する遊戯や芸術活動に割かれ、誰も彼もダイアスパーの外の世界には興味・関心を抱かない。
そんなダイアスパーには一人、生まれながらの異端児アルヴィンが住んでいる。
アルヴィンを除き、ダイアスパーの人間は皆かつてダイアスパーで生きたことがあり、メモリーバンクを経て再びダイアスパーに生れ落ちた人間である。
そのため「前世」を持っており、その「前世」の記憶まで引き継いでいるのだが、アルヴィンは久方ぶりに表れた「前世」のない人間。
全く新しい人間としてダイアスパーに生まれてきた人間だった。
そんなアルヴィンは昔からダイアスパーの在り方に疑問を感じ、ダイアスパーの外部世界への関心を密かに抱き続けていた。
ある日、<道化師>であるケドロンと出会ったアルヴィン。彼との行動を通じ、アルヴィンはダイアスパー外部へ通じる道を発見してしまい.......。
「完璧」な都市ダイアスパーの秘密、外部の世界との触れ合い、世界の真実。
閉鎖された世界でただ一人「探求心」を持った冒険家アルヴィンが辿る運命とは......。
感想
冒頭にも述べましたが、閉鎖された完全都市ダイアスパーの描写は見事なものです。
その背徳的なまでの無味乾燥な美しさはまさに未来の"理想"都市を皮肉という意味でよく表現しています。
かつては「銀河帝国」を形成して宇宙に覇を唱えていた人類がなぜかいまは地球上のいくつかの都市に引きこもっているという設定にも関心がそそられます。
また、ダイアスパーでの生活もまさにSF的近未来。
ユートピア的ディストピアとでも言うべきものです。
いわゆる労働は全て機械が行っており、人間生活は「サーガ」と呼ばれる仮想空間での冒険や、絵を描いたり音楽を奏でたりという芸術活動に捧げられたおります。
機械化AI化とベーシックインカム的な政策により実現可能だと言われている世界に近いでしょうか。
また、衣食住は保障されているのですが、食事は合成食であり、動物が存在しない世界であるなど、どこか異様な無色感が漂っているのも物語の始まりに不穏な空気を与えていていい味を出しています。
さて、こういった世界に青年アルヴィンが生活しているわけですが、全住民の中で彼だけが世界に疑問を覚えているという設定もまたベタながら主人公感があります。
そして、彼が出会う<道化師>のケドロン。<道化師>というのはこのダイアスパーに時おり生れ落ちる特別な役割を持った人間のことで、いわばこの秩序と規律に溢れているがゆえにつまらない世界をちょっとした悪戯で盛り上げることが彼の仕事です。
しかしもちろん、その悪戯さえもコンピューターによって仕組まれたもの。
ケドロンがコンピューターによる制御を覆すような悪戯をすることはなく、まして、外の世界に飛び出したり外の世界の事象を内に引きこもうとすることはありません。
むしろ、そういった適度なかき乱しによってガス抜きをする存在、「パンとサーカスによる統治」の道具なのです。
しかし、ケルヴィンが彼から受ける影響は他のダイアスパー市民とは異なるものです。
ケルヴィンはケドロンとの行動を通じて外の世界への入り口を発見し、外界の都市リスへ辿り着きます。そこで出会った人々は、テレパシーで会話し、生殖によって子供をもうけ、動物とともに暮らし、合成食ではない食事を摂る人々。














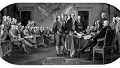
コメント