この需要側の文化が、ますます供給側の姿勢を固定化させていくスパイラルがあるのです。
さらに、「住宅双六」の終着点が「新築」持家であることにも本書は注目します。
中古の持家を買う、というのは日本ではあまり馴染みがありませんが、米英仏では住宅流通に占める既存住宅(=中古)の割合が70~90%に達しており、10~20%の日本とは全く異なる住宅市場が形成されております。
中古市場での利用を前提としないため日本の住宅価値滅失速度は非常に早く、まるで穴の開いたバケツに水を投じるように、ひたすら新築住宅にお金を投じ続けて住宅の供給を維持しているのが現状なのです。
それでは、なぜ諸外国と日本とではこのような市場性質の違いが出てくるのでしょうか。
本書はここでも取引コストに注目し、特に中古住宅は新築住宅よりも取引コストが高い(住宅の質の判断が難しい、欠陥を取引業者が隠しているかもしれない)ことを挙げております。
本書ではさらりとしか触れられておりませんが、諸外国では専門家が第三者として住宅の検査や価格決定に関わることで、不動産業者と買い手との情報の非対称性を埋めるような制度が整っているようです。
確かに、「一生で一番高い買い物」なのですから、少しでも不安があれば「安全を見て新築で」となってしまいますよね。
それを覆して中古を流通させられるような諸外国の制度は特筆するべきものがあるのでしょう。
そして、そのような制度がない状況では中古市場が発展せず、人々はますます住宅の価値保全に興味を失くすわけです。
加えて、賃貸住宅の更新では店子の合意形成が困難な一方で、新築を立てるのはデベロッパーの一意で可能なことから、「ピカピカの住宅」は市場において「新築持家」のみとなってしまい、ますます「新築持家」文化の強化が進む点を本書は指摘します。
他にも様々な制度的・インセンティブ的要因を挙げつつ、今日の住宅市場がどのように築かれてきたのかがこの第1章では明らかになります。
さて、第1章は主として「自然状態」だと住宅市場はどのように構築されるのか(そして日本はその状況に近い)のかが解説された章といえますが、第2章では政府がどのように公的介入を行ってきたのか、ということが述べられます。
結論としては、「新築持家」文化をより助長する政策という側面が強く、公営住宅などの直接供給は「住宅双六」に乗れない人々に対する、いわば残余的供給に留まったというものです。
住宅政策の3本柱、と本書では銘打たれておりますが、公営住宅、UR都市機構、住宅金融支援機構の3つ、これらについて受ける印象は世代によって大きく異なるのではないでしょうか(昔は名前も違いましたよね)。
公営住宅や公団住宅は、一時期は中産階級にとっても非常に人気の住宅で、住宅双六の「持家以前」の段階(あるいは、当時は終着点として)にしっかり組み込まれておりました。
しかし、住宅の絶対量が充足し、中間層が自らの力でよりハイグレードな住宅双六を行っていく段階になって公営住宅や公団住宅の建設は正当性を得ずらくなり、次第に民間住宅にアクセスできない人が入る住宅となっていきます(=残余化)。
日本の最も恥ずかしい文化の一つ、「団地の子と遊んではいけません」の時代がちょうどここなのかもしれませんね。
対して、住宅金融支援機構は「持家化」の流れを後押ししていきます。
持家取得希望者に対して低金利で融資することでその行動を促進するわけです。
政府の住宅ローン減税などもこの傾向を後押しし、市場における新築住宅の建造という供給も爆発的に増やしていく結果になりました。
いまでも「フラット35」は住宅ローンの有力な選択肢のうちの一つですよね。
本書のサブタイトルは「日本における住宅と政治」ですが、上述した自然な市場形成に加え、政治もその傾向に拍車をかけ、結果的に極端な「新築持家」社会が日本に生まれたわけです。
日本に住みなれていると、「それのどこがおかしいの?」とやたらに「新築持家」を強調する本稿の筆致に疑念を抱くことも不思議ではありませんが、そう思われた方は本書p93の国際比較表を見ると目から鱗が落ちるかもしれません。
第3章は少し視点を広げて「都市計画」の話になっております。
戦後から現在にかけて一貫して続いているのが都市への人口流入であり、近年は大阪圏への流入が弱まっているとはいえ、強力なトレンドであることは間違いないでしょう。
「国土の均衡ある発展」や「地方創生」が謳われ、UターンやIターンが少しだけブームになったりもしましたが、なかなか甲斐はなさそうです。
東京や大阪に限らず、地方都市レベルでも、より「田舎」な地域から人口が流入してきていたのは誰もが知り、感じるところでしょう。
そして、そういった「移住者」を都市はどのように受け入れていったのか、というのがこの章で論じられるところです。キーワードは「スプロール(現象)」。
中学校の教科書にも載っている文言なので皆様ご存知のことでしょう。
つまり、日本において、都市は人口増加に合わせてひたすら外延へと拡大していったわけですね。
もちろん、ここにも「制度」が関わっているわけです。
都市の中心部の土地は既に住宅や商業施設で埋め尽くされており、「土地」や「持家」についての私権が非常に強い法律制度かつ中古市場が未発達のため中心部の人々はなかなか土地や住宅を手放さず、高級賃貸住宅は供給者にとって割に合わないため中心部の賃貸住宅は更新も上への拡大もなかなかされず、しようとしても店子の合意形成は極めて困難。
そしてなにより、強力な「新築持家」文化。
都市郊外を開発することへの公的規制は非常に緩い。
このような条件下で、郊外に次々と新築持家が立っていくわけです。
「ニュータウン」に見られる鉄道沿線の大規模開発地帯や、田畑の中で虫食い状に広がる住宅街は定番の光景ですよね。













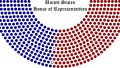

コメント