本ブログで紹介した政治学系の書籍から、政治過程論に纏わる書籍ベスト3を選んで掲載しています。
政治過程論を本格的に学びたい人のための学術書が中心となっております。
第3位 「二大政党制の崩壊と政権担当能力評価」山田真裕
2009年の総選挙(旧民主党が政権交代を果たした)を中心に、なぜ政権交代が起き、その後、なぜ政権交代が起きる気配さえなくなったしまったのか。
有権者に対するアンケート結果をもとに、その要因を統計的アプローチによって分析した学術書です。
本書では特に、選挙ごとに投票先を変更した「スウィング・ボーター」に着目し、彼らこそが政権交代の鍵になったとして「スウィング・ボーター」の属性や政策選好、各政党への支持態度の変遷を提示しております。
本書を読めば、当時民主党を支持した人々、政権交代の起爆剤となった有権者たちの実像を理解することができます。
菅政権の支持率が下がる中で野党連合は政権交代へと意気込みを高くしている状況ですが、本書を読めば「政権交代」が起こりうる状況についての学術的な造詣を深めることができるでしょう。









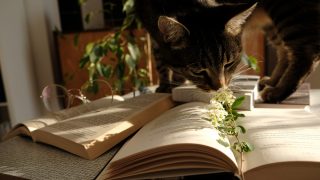
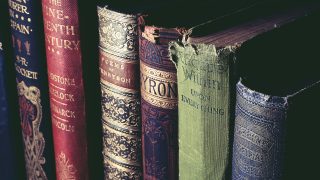






コメント