あいつは東大卒のくせに使えない。
太古の昔から鉄板となっているフレーズです。
高学歴者を新卒一括採用で入社させ、年功序列賃金制のもとでゆっくりと昇進させていく会社では陰口の定番となっている言葉なのではないでしょうか。
もちろん、純粋な嫉妬からこういった発言が出てくる場合もあるのでしょうが、事実として使えない高学歴者も存在しているのでしょう。
本記事ではなぜ高学歴者の中に使えない人間が紛れ込むのかについて考察していきます。
といっても、結論は記事タイトルで述べたとおりです。
つまり、受験勉強は利己的な行為であり、それを上手くやりきった人物が受験戦争を制するが、ビジネスや社内組織で活躍するのは(適切な形で)利他的な人物であるからです。
まず、受験勉強について分析します。
受験勉強という行為はどこまでも利己的な所業です。
全ては自分自身の能力を高めるために行われ、どれだけ受験勉強を頑張ったところで周囲の人物に対する助力にはなりません。
実利的なメリットを周囲に与えることもなければ、感動のような感情利得を与えることもありません。
あなたが受験勉強を頑張ったから、わたしは楽になった、とても助かった。
そんな事態は起き得ないでしょう。
(あなたの親が教育ママ/パパであれば喜ぶかもしれませんが、少なくともその範囲に留まります)
一方、ビジネスや仕事というものは多分に利他的な側面が重要になります。
いまをときめく新興ビジネス界隈であれ、古い組織の中でのことであれ同じです。
顧客の感情を考慮し、いかに寄り添った製品開発やサービスの提案ができるのか。
そういった、利他的な人間としての発想や行動が求められます。
社内の事務やコミュニケーションであっても同じです。
より他者を助ける人々が周囲から評価され、高いパフォーマンスを挙げます。
自分の業務範囲を広く捉えて積極的に他の人の仕事も請け負う社員。
他の社員が困っているときに手を差し伸べて困難な業務を一緒に行ってくれる社員。
あるいは、理不尽な命令にぐっと耐えながら周囲には笑顔を振り向け、誰もが嫌がる業務の集中を引き受けている社員。
そんながどの会社にも存在していて、「頼れる人」だと認識されていることでしょう。
利他的に思考し、利他的なビジョンを打ち立て、それを実行し完遂できること。
ビジネス界隈や会社組織で活躍する人々が持つこれらの要素を大学受験は測定しませんし、受験勉強ではこれらの能力を伸ばすことができません。
学校の勉強は得意でも、仕事はできない。
そういった人々に共通するのは、こういった利他的なマインドの欠如や不足なのではないかと思います。
(もちろん、ADHDなどの障がいを抱えていて、いかにも集団的な行動であったり、形式的な儀礼であったり、不条理かつ無駄に複雑な事務作業ができないという人々もいるのでしょうが)
そう考えると、特に新卒採用ではこの利他的マインドを見抜くのがコツなのではないかと思えてきます。
その人自身の絶対的能力や、何を成し遂げてきたのかという実績も重要ですが、そういった能力を他者のために使おうとするか、そういった実績はどう他者のためになったのか、そういった要素を拾っていく技量が採用側に求められているのでしょう。
補論 AO入試が救世主になる?
世間的には批判の多いAO入試ですが、思いのほかこの制度が「使えない高学歴者」を消滅させていくかもしれません。
受験勉強以外での学内・学外活動が受験で重視されるということは、社交的で積極的で、多くの人々から信頼されるような人物(リア充的人物?)がAO入試を勝ち抜くことになるからです。
ただ、旧来の偏差値的な頭の良さを一定程度無視することになるので、その弊害は起こりうるかもしれません。
ビジネスや会社組織維持を行うために、偏差値的な頭の良さもそれなりには寄与しているでしょうから。
当ブログを訪問頂きありがとうございます
応援クリックお願いします!




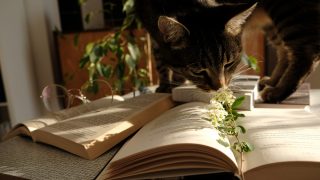













コメント